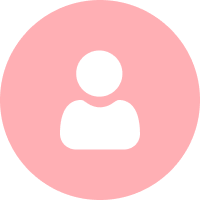ChatGPT、Perplexity、Claudeといった生成AI検索・対話エンジンが、ユーザーの情報探索プロセスに急速に浸透する中、検索体験そのものが劇的に変わりつつあります。
かつては、SEO(検索エンジン最適化)によって検索順位を上げ、サイト流入やブランド露出を高めることがマーケティングの常識でした。
しかし現在、検索結果(SERP)のリンクをクリックするのではなく、AIが統合・生成した“直接的な答え”だけで完結するケース「ゼロクリック検索」が主流になりつつあり、従来のSEOが持つ影響力は確実に低下しつつあります。
この新たな環境で注目されているのが「AI Visibility(AI可視性)」という新しい指標です。
これは、検索順位ではなく、生成AIによる回答や会話の中で、ブランドが登場するか・信頼されているか・引用されているか・優先的に紹介されているかといった、“AI上での存在感”を測るものです。
コンテンツ
AI Visibilityとは?検索の未来を定義する新指標
AI Visibility(AIビジビリティ/AI可視性)とは、ChatGPT、Gemini、Claudeといった生成AI・会話型AIにおいて、ブランドや商品、サービス、コンテンツがどのように「認識され」「信頼され」「言及され」「引用・推薦されるか」を示す新たな指標です。
これは、単なる表示回数(インプレッション)のような数字上の露出を指すものではありません。新しい検索体験の中で、ブランドが「AIによる回答の中に登場するか」「どのように描写されているか」「信頼の置ける情報源として扱われているか」など、文脈と質を含めた“見え方”全体を指します。
従来のSEOが「検索順位」や「クリック数(CTR)」に焦点を当てるのに対し、AI Visibilityは次のような観点に注目します。
- AIに質問したとき、自社のブランドや商品が回答に含まれるか?
- 言及される際、その内容はポジティブか、ニュートラルか、あるいはネガティブか?
- 主要な回答として提示されているか? 信頼できる情報源として、リンク付きで引用されているか?
- 複数のAIツールや、様々な質問の意図(インテント)に対して、安定して表示されるか?
なぜ今、AI Visibilityが重要なのか?
- 検索行動の根本的な変化: 検索ユーザーはもはや「キーワード入力→検索結果クリック→サイト訪問」といった従来のステップを踏まず、AIに直接問いかけ、即座に“まとめられた答え”を得るスタイルへ移行しつつあります。この変化により、ブランド露出の主戦場は「検索結果」から「AI回答」へとシフトします。AIの回答に登場しなければ、そもそも存在を認知されません。
- 従来のSEO指標では測れない可視性がある: 従来のSEO指標(検索順位・CTRなど)では、AIの回答領域でのブランド露出は測定できません。AI Visibilityは、AIが自社をどう言及するかという“ブランドの声量”や“ポジティブな引用”の可視化に焦点を当てており、PRやブランドマネジメントの延長線上にある新たな概念です。
- ゼロクリック検索が当たり前に: ChatGPTは週あたり4億人以上のアクティブユーザーを抱え、Googleの「AI Overview」も多くの検索でAIによる要約を表示するようになりました。こうしたAI回答を見て、リンクをクリックせずに検索行動を終える「ゼロクリック」が急増。リンクされない=発見されないという構図がより明確になっています。
AI Visibilityを計測する4つの重要指標
AIツールにおけるブランドのパフォーマンスを理解し、評価するためには、以下の指標が重要です。
- ブランド言及回数(Brand Mentions):AIが自社名をどの程度頻繁に取り上げるか。リンクの有無にかかわらず“言及”自体が価値です。
- 引用ソース(Citations):ブランドのウェブサイトがリンク付きで引用された回数。これはトラフィック獲得に繋がるだけでなく、AIプラットフォームがそのコンテンツを信頼している証でもあります。
- 言及シェア(Share of Voice):特定のトピックについて、AIが生成した回答の中で自社ブランドが言及された割合。競合他社との比較基準として活用できます。
- 言及の文脈(Context of Mentions):ブランドが「第一候補」として推奨されているか、「選択肢の一つ」か、あるいは「軽く触れられた」だけか。その表現はポジティブか、客観的か、曖昧か。これらはユーザーのブランドに対する第一印象や信頼度に直結します。
AI Visibility計測・分析ツール5選
AI Visibilityを測定・分析するためのツールが既に登場しており、マーケターに新たな分析手法を提供しています。
- Profound:ユーザーの質問をシミュレーションし、主要なAIツールにおけるブランドの表示状況(説明内容、順位、推定トラフィックなど)を分析します。
- AIVily:世界初のAI Visibilityを主軸に設計されたトラッキングツールを謳い、複数プラットフォームでの露出比較や言及シェアのトレンド追跡機能を提供します。
- Peec AI:複数のLLM(大規模言語モデル)プラットフォームを横断し、プロンプトごとのブランド露出を分析。時系列での変化や、AIのバージョンによる回答の違いも観測可能です。
- Otterly:プロンプトを新たな「検索キーワード」と捉え、地域や言語の特性に応じたきめ細やかな追跡を実現。カスタムトピックでの追跡や品質評価もサポートします。
- HubSpot AI Search Grader:ブランドがAI検索結果に表示されるかを迅速に評価し、基本的なアドバイスを提供する入門ツールです。
AI Visibility計測における「データの壁」
前述のツールは、AIにおけるブランドの可視性を測る助けとなりますが、そのデータの多くは「間接的な推計」に基づいています。
- AIプラットフォーマーは内部データを公開しない:GoogleやOpenAIといった主要なAIプラットフォーマーは、AIの回答におけるブランドの引用頻度や、参照したコンテンツのリストを公開していません。
- 生成結果は毎回変動する:たとえ同じ質問をしても、時間やユーザーが異なれば回答も変わる可能性があり、結果の一貫性を担保することが困難であることに留意しなければなりません。
- 出典表示の基準が未整備:AIツールが必ず引用元を明記するとは限らず、時には存在しない出典を捏造(ハルシネーション)したり、元の文章が特定できないほど内容を書き換えたりする可能性もあります。
そのため、現状の観測手法は次のようなアプローチに頼っています。
- 膨大なプロンプトを作成し、さまざまなテーマや質問パターンでテスト
- クローラーを使って、AIプラットフォームの回答内容を継続的に記録・収集
- 既知のAIクローラー(Google-Extendedなど)の活動や自社サイトのサーバーログを分析し、AIによるコンテンツの取得状況を推定する
- Google Search ConsoleやGA4のデータを組み合わせ、AIによる検索トラフィックをクロス分析によって推定する
これらの手法は100%の正確性を保証するものではありませんが、現段階では最も信頼性の高い計測アプローチと言えます。
プラットフォーマーがデータを公開しない理由
AIプラットフォーマーがデータを開示しない背景には、以下の事情があります。
- ビジネス上の機密保護:ブランドやコンテンツの引用・ランキングを決定するアルゴリズムは、プラットフォームの競争力の源泉そのものであり、開示することはできません。
- コンテンツ操作の防止:引用ロジックを公開した場合、悪意のある第三者がプロンプト設計(プロンプトインジェクション)などの手法を悪用し、意図的にブランド露出を増やすといった不正行為につながる恐れがあります。
- 技術的な実装の限界:生成AIは、事前に学習したコーパス(テキストデータ)と、リアルタイムで取得したWeb情報の両方を混在させて回答を生成するため、「どこから引用されたのか」を厳密に切り分けて追跡することが技術的に困難です。
唯一Googleが「Search Console」にAI検索(AI概観)のパフォーマンスデータを統合すると発表していますが、、現時点ではテスト段階にとどまっています。
AI Visibilityの未来:今後のトレンドと進化の方向性
現状、AI Visibilityの観測は外部ツールによるシミュレーションデータに依存していますが、その重要性はもはや無視できないレベルに達しており、今後、企業のマーケティング戦略における重要KPIとしての役割を強めていくと予測されます。
- プラットフォーマーへの情報開示圧力の高まり:ブランドや出版メディア、規制当局からの圧力により、AI回答での引用頻度やクリック率など一部データの公開が進む可能性があります。
- 技術革新により追跡精度が向上:新世代の引用追跡技術(MITが開発したContextCiteなど)や、LLM自体に組み込まれる出典明記機能により、AIの回答の出所がより明確で検証可能になりつつあります。
- AI Visibilityがマーケティングダッシュボードに統合される:将来的には、プロンプト管理、感情分析、競合モニタリング、コンバージョン分析といった機能を統合した“意思決定支援ツール”へと進化することが考えられます。
- AIの引用ロジックに対応したコンテンツ戦略(LLMO)の本格化:今後、Webサイト構造・記事タイトルの設計をAIに好まれる形式へ最適化する動きが広がるのは間違いありません。
結論、AI Visibilityは、これからのブランド競争力を左右する鍵です。生成AIによる検索が主流になりつつある今、AIの回答に登場しないブランドは、ユーザーの視野にすら入らない。それが新時代の現実です。
AI VisibilityはSEOを代替するものではありません。むしろ、SEOと並走しながら、AI空間における“見え方”を制するための新たな戦場です。 企業は主体的にリソースを投じ、可視性を測る指標を整備し、コンテンツ構造を最適化し、信頼されるブランドとしての権威性を確立することで、単に「検索される」存在から、「AIに推奨され、信頼される」存在へと進化しなくてはなりません。
そして、その全ての土台は、依然としてSEOです。なぜなら、AIの回答は現在も、質が高く、更新頻度が高く、構造が明確なWebコンテンツに大きく依存しているからです。
つまり、まずはSEOで土台となるコンテンツを築き、そのうえでAI Visibilityによって、AIによるブランドの見え方と評価を継続的に観測・改善していく。この二軸の戦略こそが、未来のコンテンツマーケティングにおける勝ち筋となるのです。
AI Visibilityに関するよくある質問(Q&A)
Q1:AI VisibilityはSEOの代替ですか?
A:いいえ、両者は補完関係にあります。SEOでコンテンツの土台を固めることが、AIに引用されやすくすることに繋がります。そしてAI Visibilityは、その新しい検索の世界で自社ブランドがきちんと評価され、見つけてもらえているかを測るための指標です。
Q2:AIに自社を積極的に取り上げてもらうには?
A:従来の検索エンジンのように、直接的に順位を操作することはできません。しかし、ウェブサイトの信頼性や専門性を高め、コンテンツを明確に構造化し、権威あるサイトから被リンクを獲得するといった施策を通じて、AIに引用される確率を高めることは可能です。
Q3:現在、どのようなコンテンツがAIに好まれる傾向にありますか?
A:多くのAIツールは、メディア、学術機関、長年にわたり専門分野で運営されているサイトといった「権威ある情報源」や、明確なQ&A形式など「構造化されたコンテンツ」を好む傾向があります。これらの特徴を意識してコンテンツを作成することで、言及される可能性が高まります。
Q4:自社サイトがAIに引用されたかどうかを確認する方法は?
A:Profound、Peec AIといった分析ツールを使い、引用状況をモニタリングするのが一つの方法です。また、GA4やSearch Consoleでトラフィックソースの変化に注意を払い、サーバーログでAIクローラーの巡回履歴を確認することも有効です。
Q5:AI Visibility戦略は、何から始めればよいですか?
A:以下の4つのステップで始めることをお勧めします。
- 現状分析とキーワードの洗い出し:自社の主要製品やサービスについて、ユーザーがAIに投げかけるであろうプロンプトや具体的な質問文をリストアップします。
- 観測ツールでAI上の可視性を測定:ProfoundやPeec AIなどの専用ツールを使い、自社ブランドがAIの回答にどのように登場しているかを把握する。
- サイトコンテンツの構造・信頼性を最適化:AIに引用・参照されやすいよう、ウェブサイトのコンテンツ構造、情報の鮮度(更新頻度)、そして権威ある外部サイトからの被リンクを強化します。
- 継続的な監視と改善:定期的にパフォーマンスをレビューし、競合他社の動向やAIの挙動の変化を常に監視しながら、コンテンツ戦略を柔軟に調整し続けます。
awoo AIのEコマースマーケティングソリューションやAIトレンドやLLMOについて知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。